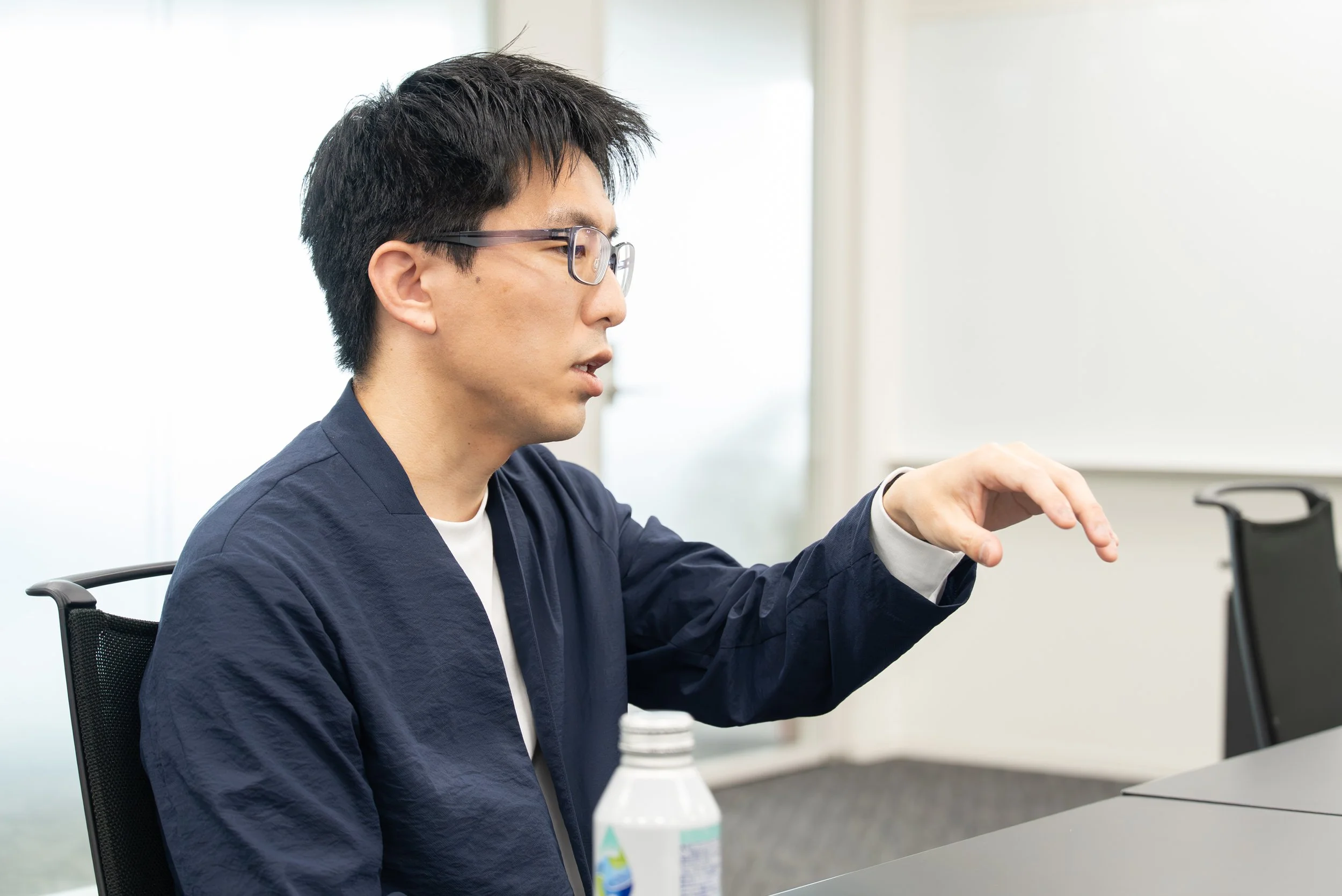博士 ×「世界に誇れる技術開発」|白幡 晃一(富士通株式会社)
2025.08.01
白幡 晃一 氏(富士通株式会社 人工知能研究所 生成AI CPJ)
博士人材 の活躍が企業の技術戦略においてますます重要視されるなか、富士通株式会社では、生成AIを含む先端領域において博士人材が重要な役割を担っている。今回お話を伺ったのは、人工知能研究所 生成AI CPJ (コアプロジェクト)の白幡晃一氏。ディープラーニング黎明期から研究に携わり、日本語LLMの開発を牽引してきた白幡氏に、博士課程で培った専門性の活かし方や、多分野の専門家と共創する現場での工夫、そして未来の博士人材へのメッセージを語っていただいた。
インタビューアー:鬼頭 祐介(株式会社アカリク ヒューマンキャピタル事業本部 事業推進部)
鬼頭 まずは貴社の事業概要について、簡単にお話しいただけますでしょうか。
白幡 はい。富士通の事業全体についてですが、もともとはコンピュータなどの製造業を主軸にしていた会社です。その後、ITサービスという形で、特にシステムインテグレーションをはじめとするソフトウェア領域まで事業が拡大してきました。
最近ではさらに、事業モデル「Fujitsu Uvance(ユーバンス)」のような、「オファリング」と呼んでいる、単に情報システムを提供するのではなく、お客様の課題解決型のソリューションを提供しています。つまり、基盤となる情報システムを導入するだけでなく、AIや必要なコンピューティング、セキュリティ技術などを組み合わせて、お客様の課題そのものを一緒に解決していく、そういった方向に進んでいます。
たとえば「Sustainable Manufacturing」(製造業向け)、「Healthy Living」(健康・医療分野)、「Customer Experienceの向上」、そして「Trusted Society 」(社会基盤の信頼性)など、具体的なテーマに向けて高付加価値なサービスやソリューションを展開しています。
つまり、デジタルトランスフォーメーション(DX)を進めるお客様を支援することが、今の富士通の主要な活動になっているということですね。
鬼頭 なるほど。そうした中で研究所の位置づけについてはいかがでしょうか?
白幡 研究所の役割としては、まさにそのDXの実現に向けて、AIやコンピューティング技術などを駆使して、お客様の複雑化した課題を解決していくことです。
例えば、物流分野であれば、配送の最適化アルゴリズムの開発、新しい素材や薬の開発においては、試作に時間がかかるため、シミュレーションとAIを活用して効率化するなどです。
こうした「お客様の課題をいかに加速して解決するか」「より難しい課題にどのように技術で向き合うか」という点に注力しています。
鬼頭 より高度な課題を解くために、デジタル技術だけではなく、広い領域においてさらに研究をしていくことの重要性が増しているということですね。
白幡 はい。ITシステムを納めるということに加えて、今後はお 客様のいろんな課題を解決していくということにもより、注力していくところになってくると思います。
そういう意味では、「研究」というものの位置づけも変わってきています。今までは「コンピュータを作る」ということが研究の主眼になっていました。もちろんそれは、たとえば理化学研究所と共同開発したスーパーコンピュータ「富岳」であったり、その次のシステムに向けた取り組みであったり、重要なことであることにかわりはありません。
しかし現在では、ハードウェア、つまりコンピュータそのものを作ることに加え、そこにソフトウェアやAIが加わり、実際の課題解決に近い領域まで対象が広がっており、研究の重要性が一層増していると感じています。
鬼頭 そのような広がりが研究所の進化を物語っているのですね。では、その研究所の中で白幡さまご自身は、どういった役割を担っていらっしゃいますか?
白幡 私は現在、人工知能研究所で、生成AIの研究を推進する立場として取り組みを行っています。具体的には、当社は特にB2Bのビジネスを展開していますので、お客様も企業が中心になります。そういった企業において、生成AIをいかに最適に活用できるようにするかという点に焦点を当てて、研究を進めています。
その中の一つとして、当社では「Takane」と呼んでいる大規模言語モデルがあるのですが、これは企業向けに特化・強化したようなモデルです。
たとえば、企業の中で登場する比較的複雑な文章―たとえば決算報告書のように、やや難解な書き方がされているものや、法律文書など―こうしたものを、正確に読み解くことができるように設計されています。また、大規模言語モデルそのものの開発に加えて、それをどう活用するかという仕組み全体の構築にも取り組んでいます。
少し踏み込んでお話しますと、大規模言語モデルというのは、大量のデータを事前に学習しているため、ある程度の知識は持っています。ただし、企業の中には、インターネット上に公開されていないデータがたくさんあります。そういった社内に閉じたデータというのは、通常のモデルでは学習されていませんし、見ることもできません。ですので、企業内で生成AIを活用していく際には、そうした社内データをいかに活用できるようにするかが、大きな課題の一つになってきます。
そのために、まず社内の文書を正確に検索できるようにする、といった技術の開発にも取り組んでいますし、それだけではなく、必要に応じて追加のデータでモデルを 再学習させることもできます。
つまり、お客様ごとにLLM(大規模言語モデル)自体をカスタマイズして提供する、ということも可能です。さらに、そのための仕組み自体をお客様に提供することも視野に入れています。
こうした取り組みを通じて、それぞれのお客様の業種や、個社ごとの固有の課題により深く入り込み、その課題を解決できるような技術開発を進めている、というのが、私たちの現在の活動になります。
鬼頭 なるほど。現在、生成AIや関連ツールの業務利用というのは、かなり一般的になりつつあると感じます。そういった中で出てくる、より具体的で個別なニーズに対応するための重要な研究に取り組まれているのですね。
鬼頭 そのように研究に力を入れている環境では、博士人材と呼ばれる方も多くいらっしゃるのではと思うのですが、チーム内にはどのくらいの方が在籍されているのでしょうか?また、どのような分野の方がいらっしゃるのかについても、ぜひお伺いできればと思います。
白幡 当社にはかなり多くの博士が在籍しています。特に「富士通研究所」という研究組織があり、Computing、Network、AI、Data & Security、そして人文系技術との融合を目指すConverging Technologiesという、5つの技術領域に注力しています。こうした多様な研究分野で、博士号を持つ人材が活躍しています。社会課題がますます複雑化・高度化するなか、それに立ち向かうには、やはり博士人材のような高い専門性を持った人たちの力が欠かせません。
「どんな分野の博士がいるのか」という点も面白いところでして、実はコンピューターサイエンスに限りません。たとえば物理系の博士もいます。AI、特にニューラルネットワークは、人間の神経系を模した構造で成り立っているので、脳の構造や神経活動といった知見が重要になってきます。コンピューターサイエンスだけでなく、物理学など他分野とも非常に密接に関係しているものです。
実際、量子力学とニューラルネットワークの理論が近いと言われることもあります。昨年(2024年)のノーベル物理学賞ではAI関連の研究が評価されました。その例からもAIと物理学は非常に深い関係にあるということがわかります。
弊社では、コンピューターサイエンスに限らず、理論に強い方であれば、さまざまな分野の人材が活躍できる可能性を持っています。大学での専攻と企業での活躍が必ずしも直結しているわけではなく、多様なバックグラウンドを持った方々が、それぞれの強みを活かして働いています。
たとえば「創薬」と呼んでいる取り組みがあります。これは薬をつくるという、もはやコンピュータそのものの話ではなく、それよりもさらに上のレイヤーの研究になります。こうした分野まで含めて、今では従来の「コンピュータを作る会社」の枠を超えた研究が行われており、確実に研究の幅が広がっています。
そのぶん、たとえばシミュレーションができる人材や、より応用寄りの専門性を持った人材の重要性も増してきています。研究対象や求められる能力の範囲も、確実に広がっていると実感しています。
鬼頭 たしかに、量子力学やニューラルネットワークに関わるような方々、あるいは先ほどお話に出ていた創薬や素材のシミュレーションのような領域になってくると、マテリアルインフォマティクスのような分野の専門家も、ご活躍されているイメージが湧いてきます。
そう考えると、本当にコンピューターサイエンスに限らず、さまざまなバックグラウンドを持った方が関わっていらっしゃるのですね。改めて、領域の幅広さや奥行きのある取り組みであることを実感しました。
鬼頭 ここからは、少し白幡さまご自身について伺えればと思います。 博士課程でのご専門や、入社当初のお仕事について教えてください。
白幡 博士課程では、スーパーコンピュータを使ったビッグデータ処理の高速化に取り組んでいました。
今では当たり前のGPU搭載のスーパーコンピュータも、当時はまだ珍しく、東京工業大学(現 東京科学大学)が開発していた新型のスーパーコンピュータ上で、いかに効率よくビッグデータを処理できるかがテーマでした。
ちょうど「ビッグデータ」という言葉が注目され始めた時期で、今後重要になると言われていた中、私はシステムソフトウェアの設計やアルゴリズムの開発、実装・評価まで一通り手がけていました。
学生時代から、「スーパーコンピュータを活用して社会課題をどう解決するか」に強い関心がありました。
そうした背景もあり、当時「京(けい)」の開発を進めていた富士通に注目しました。日本発で、世界と伍するような技術開発を実際に行っている会社ということで、とても強い興味を持ちました。
世界に通用する技術を日本発で開発している企業として魅力を感じ、「自分もその一端を担いたい」と思って入社しました。
入社後に最初に関わったのは、ディープラーニング、いわゆる深層学習の研究です。ちょうどその技術が注目され始めた頃で、「スーパーコンピュータの計算資源を使って、いかに効率よくディープラーニングを実行するか」というテーマが立ち上がろうとしていました。
私はまず基礎から学び、CNN(畳み込みニューラルネットワーク)を自分で一からプログラミングして動かし、画像分類などのタスクで学習が正しく行われているかを検証しました。また、ネットワークの内部挙動を観察しながら、部署内で仕組みや設計のポイントを説明するなどの役割も担っていました。
その後は、「このモデルを効率的に動かすには、どんなハードウェアが必要か?」という視点からも検討を始め、ソフトとハードの両面からディープラーニングの性能最適化に取り組んでいきました。
鬼頭 まさにディープラーニングの走りの時代だったと言えると思います。確かにあの頃は、そういった研究成果が次々に出てきて、私自身もそれをよく目にしていた印象があります。とても勢いのある時期でしたね。そもそも白幡さまが博士課程に進まれたご理由や、当時どのようなことを考えていらっしゃったのか――そのあたりもお伺いしてもよろしいでしょうか。
白幡 そこは実はかなり悩みました。もともと企業にも興味がありましたし、最初から就職したほうが良いのではないかと考えたこともあります。ただ、やはり新しい技術をつくっていくためには、専門性をいかに高めるかが非常に重要だと感じました。
情報系の分野だったこともあり、博士課程に進んだからといって就職に不利になるというような印象は自分の中では特にありませんでした。それであれば、難しい道かもしれないけれど、専門性を高めておいたほうが将来的に活躍できる可能性が高まるのではと考え、博士課程進学を選びました。
鬼頭 たしかに情報系の分野では比較的進学後のキャリアの選択肢も多い印象ですね。ところで、余談ですが、アカリクのイベントにもご参加いただいたと伺いました。当時は博士課程の学生さんだったのですか?
白幡 はい、そうです。博士課程在学中に参加しました。イベントを通して企業からのオファーや選考の案内などをいただく中で、やはり世界的に競争力のある技術開発をしていきたいという思いがあり、最終的に富士通への入社を決めました。
鬼頭 入社後は、ディープラーニングの処理をスパコンでどう効率化するかという研究に取り組まれていたとのことですが、その後のキャリアの流れについても教えていただけますか?
白幡 最初の数年間は、そうしたディープラーニングとスーパーコンピュータに関する研究を継続していました。その後「富岳」が出てくることになり、その上でのディープラーニング処理、また新薬の開発に関わるものや、構造力学、流体力学など、さまざまなシミュレーションの高速化といった領域にも取り組むようになりました。
その後、マネージャーになってからもコンピューティングという軸は変わらなかったのですが、あるとき「MLPerf」という、機械学習の処理性能を競うベンチマークに挑戦するプロジェクトが立ち上がりました。
「富岳」を使って世界一の性能を出そうという目標があり、大きなチームを組んで取り組んだのですが、私はそれをリードする立場で参画しました。最終的に、実際に世界一の性能を達成することができたのは、大きな経験でした。
さらにその前後には、材料開発、海外のスタートアップであるAtmonia社と協業し、クリーンエネルギーに関する触媒材料の研究も行っていました。AIやシミュレーションを活用して新しい材料を探索するというテーマで、これも立ち上げから関わった思い入れのあるプロジェクトです。
そして、その後にやってきたのがLLM(大規模言語モデル)の開発です。
ちょうどアメリカでは技術が先行している中で、日本国内でもLLMを開発しようという機運が高まっていました。名古屋大学や東京工業大学 の先生方、さらにはアメリカの大学院生など、さまざまな立場の人たちが「富岳を使って日本独自のLLMをつくろう」と声を上げたんです。
私自身がこのプロジェクトを最初に提案したわけではありませんが、入社時の動機でもあった「世界に誇れる技術開発」を実現するチャンスだと強く感じて、プロジェクトに参画しました。
このプロジェクトは 2年前に始まり、昨年春に一区切りを迎えましたが、現在の「Takane」や企業向けLLMは、この流れから生まれています。
現在はコンピューティング研究所から人工知能研究所に所属を移し、AIそのものの研究に本格的に取り組んでいるという状況です。
鬼頭 技術の発展とともにキャリアを構築され、常に最先端の分野に関わってこられた印象を受けます。そうした中で、一研究者からマネージャー、プロジェクトリードへと変わっていく過程で、ご自身の中でどのような変化がありましたか?
白幡 役割の変化とともに、考える視点も変わってきました。最初から「一人で難しいことをやるのは限界がある」という認識は持っていたので、チームで成果を出すためにどう動くかという視点が重要になってきました。
チームメンバー一人一人の能力をいかに活かし、全体として大きな成果を出すかということを常に考えるようになりました。これは、個人では達成できなかったようなことが可能になるという意味でも非常にやりがいのあるポジションです。
鬼頭 ここまでさまざまな最先端の研究に取り組まれてきた中で、「博士課程での経験が生きたな」と特に感じた場面について、お聞かせいただけますか?
白幡 それはもうかなりいろんな場面で活きていますね。マネージャーになると、研究テーマの立案など、考える範囲が広がります。修士課程までは、比較的短期で与えられたテーマに取り組む印象ですが、博士課程では、自分でテーマを設定し、長期的に成果を出す必要があります。そこで求められるのが、自立した研究姿勢や、プロセス全体への責任感です。
テーマ設定から開発、発表までを自分で回した経験があると、マネージャーとしてもプロジェクト全体を俯瞰して判断できる力が身につきます。
また、博士課程では学会発表や海外発信も多く、成果の出し方・見せ方の感覚も磨かれます。それが、企業での研究にも大きく活かされています。分業が基本の企業でも、全体を経験していることで、どんなポジションでも的確に動けるし、チーム全体を支える力にもつながっていると思います。
鬼頭 では逆に、博士人材として産業界に入ったときに感じたギャップや苦労はありましたか?
白幡 あるとすれば、「博士だから当然これくらいはできるだろう」という周囲の期待感ですね。
期待されるのはありがたいことですが、そのぶん「応えなければ」というプレッシャーも少しありました。ただ、それをネガティブに感じたわけではなく、自然なこととして受け止めていましたが。
鬼頭 期待値を超えるアウトプットを出さなければ、というプレッシャーのなかで、大変なこともあったと思うのですが、特に印象深いエピソードがあればぜひ教えてください。
白幡 どれかひとつを挙げるとすれば、やっぱり最近のLLMの開発です。
地震が起きたときの避難経路をどうするかなど、国レベルのさまざまな課題に対応するため、「富岳」は非常に広い分野のアプリケーションに対応したスパコンになっています。これはこれで素晴らしいのですが、AI向けに特化されたものではありませんでした。まだLLMが存在しなかった時期に「富岳」が完成したという背景もあります。
だからこそ、LLMの開発を「富岳」で行うというのは、非常にチャレンジングでした。特に日本語を中心としたデータを集めて、日本ならではのLLMをつくろうというプロジェクトだったので。
このプロジェクトでは、「富岳」の専門家、LLM開発の専門家、日本語データの専門家など、それぞれが異なる強みを持っており、全員が必要でした。一人では到底成しえない挑戦で、みんなで知恵を出し合いながら進めました。
たとえば学習を開始するだけでも困難で、動作させることすらすごく大変なんです。ようやく動いたと思ったら、予期しない挙動を示したり、学習が進まなかったり。問題は山積みでした。それでも大学の先生方の助言も得ながら、一つひとつ課題を乗り越えて、最終的には国産LLMの開発にこぎつけた、というところはありましたね。
鬼頭 とても面白いお話ですね。やはり個人で行う研究とは異なり、大規模な技術開発では、専門分野が異なるメンバーが集まってチームで取り組む必要がありますね。
白幡 自分にとってもこれほど大規模なチームは初めてでした。通常は2〜3機関程度の共同研究が多いなか、7機関が共同研究を行うというプロジェクトでしたから。
当然、意見の対立、食い違いも多かったんですね。それでも、すべてを自分たちの主張通りにするのではなく、相手の意見に納得して従うことも心がけました。とにかく、全体としてまとまらなければ成果にはつながらない。社内外とかなり密に連携しながら、チームで進めていきました。
鬼頭 専門が違えば言葉の定義も理論体系も違いますし、そのすり合わせは相当大変だったと思います。
白幡 だからこそ、自分たちがわからないところについては、信じるしかない。全てを理解することは不可能ですから、お互いに信頼して進めていました。
鬼頭 まさに“背中を預け合う”ような感覚ですね。
鬼頭 続いて、白幡さまご自身の経験から見た、博士人材の強みについてお聞かせください。
白幡 そうですね。私が以前いたコンピューティング研究所では、私はソフトウェア寄りでしたが、ハードウェアまで詳しい方がいて、その中には博士人材が多くいました。
高効率に動作するコードを書くためには、コンピュータアーキテクチャに非常に精通した人の存在が不可欠です。
我々のチームにも、CPUの挙動まで 理解した上で、限界まで性能を引き出すプログラムを書くような方がいました。そういう人って、やっぱり「この領域に関しては誰にも負けない」っていう、強烈な専門性を持っているんですよね。ほかの人にはとても太刀打ちできないような。
もちろん、まんべんなく何でもできる人も重要ですが、特定分野で圧倒的に強い人がいることで、そこを活かして、他では出せないような尖った成果が出せたりする。だから、そういう強みを持った人が数人いると、技術としてすごく強くなれる、というのは本当にあると思いますね。
鬼頭 では少し一般的な質問になるかもしれませんが、一緒に働く研究者の中で「この人は優秀だな」と感じる方に、共通する特徴はありますか?
白幡 最近よく考えるんですけど、やっぱり「熱意」ですね。特定のスキルや知識よりも、「これをなんとか成功させたい」という気持ちや、粘り強さ、あきらめない姿勢。そういう人が、最終的に成果を出す気がしています。
もちろん最低限のスキルやコミュニケーション能力は必要ですが、それは前提としてあって、その上で「絶対にやりきる」という意思があるかどうかが大きいと思います。どんなにスキルがあっても、それを発揮するにはやはり熱意が必要だと感じます。
鬼頭 確かに「やりきる力」は、どの職種にも通じる要素ですよね。
白幡 しかも、熱意は必ずしも最初から自発的にある必要はなくて、マネージャーが引き出してあげることもあると思うんです。でも、やっぱりベースに「やってやるぞ」という気持ちがあるかどうかで、結果は大きく変わってくると思います。
鬼頭 それは納得です。まさに普遍的な話ですね。では、熱意を引き出すために、白幡さまが意識していることや工夫はありますか?
白幡 難しいですね……それが分かれば苦労はないのですが(笑)。明確な答えがあるわけじゃないですが、ひとつあるとすれば、自分がまず楽しんで取り組めているか、ということです。自分が楽しいと思えていれば、その気持ちを周囲に伝えていくことは難しいことではありません。
もちろん、仕事は楽しいことばかりではありませんが、それでも「これを乗り越えたら面白いことができる」といった先の可能性を、チームに伝えることは意識しています。
鬼頭 楽しさを伝えていくのが大事なのですね。
白幡 ええ、できる範囲で。でもそれだけでなく、一人ひとりの悩みや課題に向き合うことも大事です。熱意が表に出ていないように見えても、何かしら問題を抱えていることがあるので、対話を通じて個人の状態や背景を理解するようにしています。
鬼頭 では今後、博士人材が企業でより活躍していくために必要なことは何だとお考えですか?
白幡 ひとつは、「自分の専門は企業のニーズにぴったり」というようなマッチングだけでなく、「自分の能力は、別の分野でも活かせるかもしれない」といった視点を持つことです。
同じ人でも、環境が違えば活躍度は大きく変わる。だからこそ、「どこでその人が一番力を発揮できるか」を見極める力が、企業側にも求められていると感じます。
そのためには、企業側としても待っているだけではなく、大学やイベント、学会などを通じて、さまざまな人と出会い、フィールドをつないでいくこと、出会いの機会を丁寧に積み重ねていくことがますます重要になってくると思っています。
鬼頭 では、博士課程に進もうとしている学生や在籍中の方に向けて、「今やっておくとよいこと」があれば教えてください。
白幡 私自身やってよかったと思っているのは、博士課程のときに海外インターンシップを経験したことですね。博士の時期って、意外と一番やりやすいんです。
何がよかったかというと、世界のトップレベルを早い段階で見られたこと。自分がどの位置にいて、どれくらい頑張れば届くのかという感覚が持てるようになりました。
正直、そのときは挫折に近い気持ちもありましたが、そういう経験を通じて「自分には何ができるのか」「何を強みにするのか」を考えるようになったので、できる人にはぜひ挑戦してほしいです。
鬼頭 海外インターンシップは博士課程のほうがやりやすいんですね。
白幡 はい、単純に時間の面で。企業に入ると数ヶ月のインターンシップや留学は難しいですし、修士では時間が足りない。でも博士課程なら、特に1〜2年目は自分の裁量で動きやすい時期です。
インターンシップや留学も研究の一部と捉えれば、決して研究をサボっているわけではありません。むしろ違う視点からの研究もできるので、トータルで見れば研究の質も広がると思います。
鬼頭 なるほど、それは学生にとって重要な視点ですね。では最後に、ご自身の経験から、学生が自身の研究や博士課程での経験をどう社会で活かしていけばよいと思われますか?
白幡 そうですね。私自身、就職活動のときに「ある程度経験は積んだ」と思ってはいましたが、それが社会でどう活きるのかまでは見えていませんでした。
だからこそ、自分のスキルや経験を言語化する力が重要だと思います。最近では「トランスファラブルスキル(Transferable Skill)」とも言われていますが、博士課程でも自然と身につく汎用的な力ってあるんですよね。
ただ、自分では気づきにくいので、自分の研究室の外の人たちと関わる機会を持つことが大事です。他者との対話の中で、自分の強みや特性が見えてくることも多いです。
私自身も、世界のトップを見たことで「自分はなんでもできる」と思っていた時期から、「これくらいしかできない」と限界を知った。その上で「じゃあこの道で勝負しよう」と現実的に考えられるようになったんです。
何でもできると思っていると逆に危険で、できること・できないことを見極めることこそ、これからの時代を生きていく上で大事だと感じています。
鬼頭 本日は本当にありがとうございました。私たちにとっても学びの多い時間になりました。
白幡 いえいえ。こちらこそ、お話しする中で自分自身の考えも整理できました。ありがとうございました。
本インタビューは、Fujitsu Uvance Kawasaki Towerにて実施しました
富士通株式会社の採用情報、富士通研究所、博士人材関連情報については以下よりご確認ください。
■富士通株式会社 採用サイト
https://fujitsu.recruiting.jp.fujitsu.com/
■Fujitsu TECH BLOG(研究員が様々なテーマで語る技術ブログ)
■【1日密着】博士人材の新たな未来!富士通研究員の1日
https://www.youtube.com/watch?v=zAS8LRYx1ho
■【博士のリアル】富士通社員が語る!~進学理由、就活、キャリアパス~
https://www.youtube.com/watch?v=ZA59gBPYPCA
◆ インタビューのお相手:白幡 晃一 氏(富士通株式会社 人工知能研究所 生成AI CPJ)
◆ 企業情報
社名:富士通株式会社
代表者:代表取締役社長兼CEO 時田 隆仁
所在地(本店):〒211-8588 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1
創立:1935年6月20日
こちらの記事は2025年8月1日に公開しており、記載されている情報が現在と異なる場合がございます。
Photo: 土岐 勝一郎
Writer: 小川 絵美子