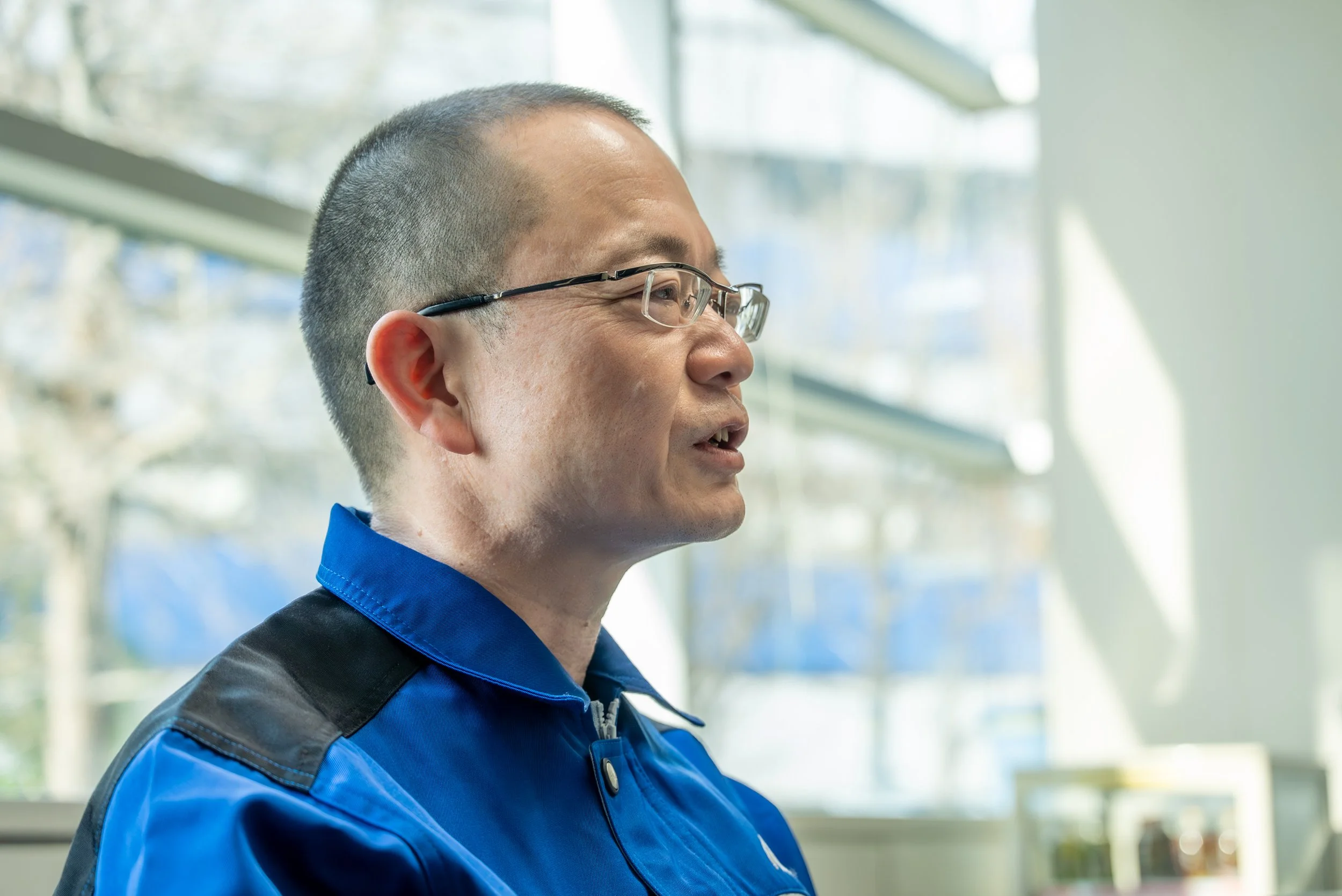博士 ×「消費財メーカー(酒類・飲料・食品)の研究職」|永富 康司(アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社)
2025.06.09
永富 康司 氏(アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社 代表取締役社長)
研究職は産業界における博士のキャリアとして代表的なポジションの一つです。アサヒグループの中長期的な研究開発を担っているアサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社では、研究職の3人に1人が博士号を保持しています。今回は同社代表取締役社長・永富氏に民間企業における研究、そしてそこで発揮される博士の強みについてインタビューしました。
インタビューアー:鬼頭 祐介(株式会社アカリク ヒューマンキャピタル事業本部 事業推進部)
鬼頭 まず始めに御社がどのような会社かを読者の方に知っていただきたく、事業概要やグループの中での位置付けからお伺いできればと思います。
永富 アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社(以下「AQI」という)は、アサヒグループにおける機能会社の一つであり、グループの中長期的な研究開発を担うことをミッションとして、2019年に設立されました。アサヒビールやアサヒ飲料といった、一般的によく知られている事業会社の所属ではなく、ホールディングス直下にある研究機能会社として、グループ全体を俯瞰しながら中長期的な技術開発や基盤研究に取り組んでいます。いわば、“事業会社を横断して支える存在”として、独立した立場から研究開発を進めている、というのが私たちの特徴です。
アサヒグループは、酒類・飲料・食品という分野でビジネスを展開する消費財メーカーですので、お客様の幸せに貢献し、社会全体に価値を提供することが使命だと考えています。
最近では「ウェルビーイング(Well-being)」という言葉もよく使われるようになってきましたが、私たちが目指すのはまさにその実現です。個々のお客様に限らず、社会全体、さらにはサステナビリティの観点から、地球全体のウェルビーイングに資するような商品やサービスを生み出していきたいと考えています。
そして、その実現に必要な新しい価値や技術の“種”を研究によって見出し、実用化に繋げていく、そうした研究活動こそが私たちの役割であり、AQIが掲げている目標でもあります。
鬼頭 アサヒグループは「スーパードライ」や「カルピス」といったお客様に馴染みの深いブランド商品に加えて、「未来のレモンサワー」などのユニークな商品を次々と生み出していますが、そうした魅力的な商品の背景には、強い研究開発力が必要だと感じています。そうなると、今回のインタビューのキーワードでもある博士人財も重要になってくると思いますが、博士人財の在籍状況について教えてください。
永富 現在、AQIには158名の社員が在籍しています。そのうち博士号を持っている人財は38名です。
この158名の中には、人事や総務などの管理部門の社員も含まれていますので、いわゆる“研究者”に絞って考えると、おおよそ3人に1人が博士号を取得している、という割合になるかと思います。
研究者の専門分野については、やはり食品メーカーという性質上、農学系や微生物系の方が多い傾向にはあります。ただ、農学系学部の出身が極端に多いということはありません。実際、私自身は薬学部の出身ですし、工学系やIT系のバックグラウンドを持つ方もいます。それは、博士号取得者についても同様です。
鬼頭 永富さまの専門領域が薬学ということですが、在学時のお話もお伺いしてよろしいでしょうか。
永富 もともと新しい薬を通じて社会の役に立ちたいという思いがあり、4年生の研究室配属時には製薬化学系の研究室を選びました。その研究室で研究に取り組んだわけですが、修士1年生の後半に、いまのままでは創薬研究者として自立するには実力が足りないと実感し博士課程への進学を考えたのが正直なところです。そうした思いから、教授に「博士課程に進もうと思います」と相談しました。その際、将来的にアカデミアの道に進むつもりはなく、博士号を取ったあとは民間企業に就職するつもりであるとも伝えました。幸い、私の所属していた研究室では、民間企業に進む博士学生も多かったので、先生からも「問題ないし、サポートするよ」と快く背中を押していただきました。
そういった意味では、食品メーカーにいる者としては、やや異色な研究分野の出身かもしれません。キャリアのスタートも外資系の製薬会社からで、新薬開発、特に化合物の合成を中心に取り組んでいました。アサヒグループは私にとって2社目になります。
鬼頭 アサヒグループに転職された契機はどういったものでしたか。
永富 あまり格好の良い話ではないのですが、2006年から2008年にかけて、いわゆるメガファーマと呼ばれる外資系の大手製薬会社が、日本から研究開発拠点を相次いで撤退していきました。ちょうどシンガポールや中国をはじめとする新興国が台頭し、日本の国際的な地位が相対的に低下した時期と重なります。私が在籍していた製薬会社の研究所も例外ではなく、その波に飲まれる形で閉鎖が決まりました。
所属していたメガファーマの研究所において、サイエンスとしては本当に最先端の研究に携わり、約8年間、非常にやりがいのある環境で研究ができましたが、一方で、自分の研究成果が実際に新しい薬になるのは非常に難しいということも実感しました。どれだけサイエンスとして優れていても、それが必ずしも新薬という成果に結びつくとは限らない──むしろ、成功する確率はごくわずかであるのが現実でした。
そうした背景もあり、せっかく民間企業で働くのであれば、もっと社会と直接つながれるような、具体的に“人の役に立つ実感”が得られる場で働きたいという気持ちが芽生えてきました。そういう意味でも、アサヒグループのような消費財メーカーには非常に魅力を感じました。
鬼頭 アサヒグループに入られてからはどのようなキャリアでしたか。
永富 私がアサヒグループに入社して最初に配属されたのは、分析化学の研究所でした。この分野は基本的に化学の延長線上にある領域で、合成化学者であった私としては非常に馴染みがあり、違和感なく業務に取り組むことができました。
配属後、まずは食品に含まれる栄養成分やリスク成分などを対象とした分析法の開発研究からスタートし、途中からは部長としてマネジメントにも関わるようになり、10年間在籍しました。
その後、1年半ほどの本社勤務を経て、2019年に設立したAQIに異動し、それから半年ほど経った頃に、かつて所属していた分析化学の研究所で所長を務めることになりました。その後、ビール会社として最も解りやすい研究分野である“酵母”や“発酵”を扱う醸造科学の研究所の所長を経験し、さらにその後、「カルピス」でおなじみの乳酸菌、特に健康機能性乳酸菌を扱う研究所の所長も務めることになりました。そうしたキャリアを経て2024年の3月に、現在のAQI社長へ就任しました。
鬼頭 多様なポジションを経験されてきた過程で、博士課程の経験が役に立った場面もあったかと思います。専門性はもちろんですが、その他に、強みへ転化した要素はありますか。
永富 私が大きなポイントだと感じているのは、「自分自身で研究テーマを考え、そのテーマに責任を持って成果を出す」という姿勢が求められる点です。
学部や修士の研究と比べて、博士課程においては、より主体性が問われます。そのため、自然と発想力のようなものが培われますし、研究がうまくいくか否かも自己責任です。自分の判断と行動が成果に直結する分、責任感が求められますし、同時に“自立性”も身につくのではないかと思います。博士課程では、誰かが代わりにやってくれるわけではありません。だからこそ、自ら考え、自ら動き、結果を出すという力が強く鍛えられるのだと感じています。
他にもマネジメント面において、研究室によって違いはあると思いますが、大半の博士課程の学生さんは、学部4年生や修士課程の学生の指導・サポートも担っているのではないでしょうか。ある程度の裁量を持って任される場面も多く、その点では、研究室内で言えば教授・准教授・助教の先生方と後輩学生との間の、いわば“中間管理職”のような立場になります。後輩学生の卒業研究の完成や、修論のサポート、さらには日々の実験の進行管理なども、自然と自分の責任として関わることになります。そういった経験を通して、学生時代から中間管理職のような立場を実際に体験できたことは、自分にとって非常に大きかったと感じています。
鬼頭 新卒で社会に出て、たとえば学部卒で働き始めた場合、中間管理職の立場を経験するまでには、ある程度の年数がかかるのが一般的です。その点、在学中にそうした経験を積めるというのは、非常に特殊で貴重なことかもしれませんね。
ところで、「企業の研究所の所長」がどのような仕事をしているのか、あまりピンとこない学生の方もいらっしゃるのではと思いました。日々どのようなお仕事をされているのでしょうか。
永富 研究所長というのは、まず研究所としての方針を定めていく立場になります。具体的には、「この分野に注力していきましょう」といった方向性を示した上で、そこに対して個別の研究テーマがいくつも立ち上がっていくことになります。そして、その方向性を実現するために必要な人的リソースや予算の確保といった部分も、所長の役割になると思います。
一方で、個別の研究テーマというのは、現場からボトムアップで上がってくることも多いです。そうしたテーマ提案に対して、「私たちが進もうとしている方向性に合っているか」「どうすれば合致させられるのか」ということを考えながら、全体をうまく調整していく必要があります。もちろん、そうした調整は一人でやるのではなく、皆で議論しながら進めていくわけですが、テーマの方向性を修正し全体を統合するのは、研究所長として求められる役割だと思います。
その際、論理的な考え方や、研究の進め方といった部分は、たとえ専門分野が違っていても、ある程度は共通していると思います。やはり、研究を始める際には、まずしっかりと下準備をして、そこからマイルストーンを引き、目標を明確にしたうえで進めていく。この基本的な進め方自体は、どの分野でも大きく変わるものではないと感じています。
もちろん、細かい技術的な内容になると、自分の専門外ではわからないことも多くなってきます。私自身も、たとえば醸造科学の研究所長を務めたときはまさにその通りで、わからないことは周囲のメンバーに聞きまくりました。部長や研究グループのリーダーは専門性が非常に高いので、わからないことを率直に聞くと、ありがたいことに皆さんきちんと教えてくれました。そして、そうしたやり取りを重ねるうちに、自分で実験をしていなくても、ある程度の知識が蓄積されていく感覚はありました。
博士課程での経験はそういった場面でも活きていると感じます。おそらく、博士課程の学生さんは、自分の研究テーマを立ち上げて進めるとき、他の研究室でどんな研究が行われているかに目を配りながら進めることが多いのではないでしょうか。また、同じ研究室の中でも、自分と違うテーマを扱っているチームの動向や進捗にも興味をもつと思います。学部生や修士課程の学生と比べて、より広い視点で研究全体を見る必要があるため、専門外の領域へ視野を広げたり、専門外の知識を吸収したり習慣が養われるのだと思います。
様々な研究設備が並ぶ実験室の様子
鬼頭 御社で博士人財を採用する理由について教えてください。
永富 博士人財の一番のアドバンテージとしては、やはり「研究や実験が本当に好きだ」というところに尽きるのではないかと思います。そういう人財の存在というのは、組織にとって非常に大きな意味を持ちます。もちろん、長い会社人生の中で、一度研究者としてキャリアをスタートしたからといって、ずっと研究職にとどまらなければならないというわけではありません。ただ一方で、研究所として継続的に価値を生み出す基盤を維持するには、やはり研究開発や技術開発に情熱を持って取り組める人が、常に一定数居る必要があります。
また、我々AQIのミッションでもある中長期的なテーマに取り組むうえでは、自らイノベーティブなテーマを創出する力や、そのテーマを推進する力が非常に大切です。その点で言えば、博士課程を経験した方は、新しいテーマの企画立案やプロジェクトのマネジメントといった面において、修士課程の学生さん以上に実績や経験を積んでいる方が多い印象です。
さらに、「博士」という肩書きがある以上、本人がそれを意識していなかったとしても、高いレベルの研究が社会的に求められます。そういった期待に応える、あるいは博士の名に恥じない研究をするという、研究に対する姿勢や矜持のようなものが博士人財には備わっているのではないかと、私は期待しています。
鬼頭 博士人財の方の貢献について、具体的な活躍のエピソードはありますか。
永富 近年、社会における健康への関心が高まるなか、「食と健康」の領域においても、非常に未来的な研究、いわゆるムーンショット的な研究が必要になってきています。博士人財の中には、臆することなくそういったテーマに挑んでいく研究者が多いですね。専門知識も社外人脈も持っているので、大学の先生方などとのコネクションを拡げながら、積極的に研究を進めてくれます。しかも、対象とする研究領域が非常に難しいということを、あらかじめ理解したうえで取り組んでいる印象があります。
そういう博士研究者たちは、うまくいかない場合のことも織り込み済みで動いており、たとえば複数のアプローチを同時並行で進めていくという先見性と柔軟性があります。目指すゴールに対して、「この手法」「あの手法」と、試しながら進めていってくれます。あらかじめ選択肢を持っておくことで、一つのアプローチが難しそうだとなれば、すぐ別のアプローチに切り替えることができる。そして、その判断も自律的に行うことができる。そうした“自分で引き際を見極める力”や“自律的な判断力と実行力”は、まさに経験豊富で専門性の高い博士人財の特長だと思います。さらに、途中で失敗したアプローチについても前向きに捉え、「当初の目的には届かなかったけれど、こういう成果や知見が得られました」という形で、何かしら結果を残そうとしてくれる。その姿勢がとても頼もしいですね。やはり本人の中にある“研究への情熱やプライド”といったものが根底にあるのだと思います。そういった姿勢を自然に持っている人財は非常に大切な存在です。
鬼頭 ちなみに、御社は様々な製品をお持ちですが、永富さまが関わってきた研究の中で製品化に繋がった事例はあるのでしょうか。
永富 私自身の経験から言えば、民間企業における研究というのは基本的にチームで進めるため、おそらく皆さんがイメージされるような、「一人で何かを生み出す」といったスタイルとは少し違っています。研究も製品開発も、多くの場合、複数人で協力しながら進めていく世界です。自分が担当する仕事は全体の中の一部であることが多いのですが、それでも、その一部が製品につながっていく場面に立ち会うことは少なくありません。
たとえば、私が実験に携わっていた分析化学の分野でも、「それが製品開発にどう役立つのか?」と思われるかもしれませんが、成分分析が必須のケースも多々あります。たとえば今、ノンアルコール飲料──いわゆる「ドライゼロ」のようなアルコール度数0.00%の製品が数多く市場に出ていますが、こうした製品を実現するためには、非常に高感度なアルコール分析が不可欠です。ノンアルコール飲料はほんの一例ですが、自分たちが開発した分析手法がそのまま製品開発に活かされるケースや、製品の品質保証や表示に直接反映されることがありました。
また、健康機能性を有する乳酸菌の研究では、私自身が直接実験していたわけではありませんが、部門内で健康効果を見出した乳酸菌素材が製品化された事例も数多くあります。そうした場面に関わることができるのが、消費財メーカーならではの面白さだと思います。
こうした「研究成果が目に見える形で社会に出ていく」経験は、決して珍しいことではなく、むしろ日常の中にある感じです。
鬼頭 関わった仕事の中で、今思うと本当に大変だったというエピソードはありますか。
永富 アサヒに転職してからは、極端に大変だと感じた場面は少なかったように思います。私が転職したのは37歳のときだったので、社会人としての経験もある程度積んでいて、困難な状況への適応が比較的容易にできたのかもしれません。
むしろ、社会人になって一番大変だったと感じたのは、製薬会社に勤めていた時期です。あの頃は、自分の研究をしながら、2つのグローバルプロジェクトのリーダーを任されていて──いわゆる“掛け持ち”の状態でした。
さらに苦労したのは、そのうちの1つのチームでは、メンバー全員が自分より年上だったことです。年下の自分がリーダーという立場でチームを引っ張るのは、なかなか簡単なことではありませんでした。
でも、そこで助けになったのが、博士課程の時に経験していた「中間管理職的な立場」の感覚でした。研究室で研究テーマのマネジメントをしていた経験が、このとき本当に活きたなと感じました。
そのときに痛感したのは、「自分がまず率先して動かないと、誰もついてこない」ということです。特に自分が年下という立場では、なおさらです。リーダーとしての行動がチーム全体に与える影響を実感した、大変でしたが良い経験でした。
鬼頭 大変な状況だったと思いますが、得た気づきは大きかったのかもしれませんね。これからのキャリアでチャレンジをする博士課程の学生の方、もしくは進学を考えている方に向けて、将来に向けてやっておくべきことのアドバイスがあればいただきたいです。
永富 よく皆さんから聞かれるのですが、その際に私が必ずお伝えしているのは、「まず、いま取り組んでいる研究をきちんと仕上げてください」ということです。つまり、しっかりと学術論文や博士論文という形にすること。そこでは、自分がやってきた研究を一つのストーリーにまとめ、それを誰が読んでも理解できる形で文章に落とし込むことが求められます。特に学術論文として外部に発表する場合には、他の研究者から疑義を持たれないレベルにまで、きちんと内容を詰めておかなければなりません。つまり、データの信頼性やストーリーの論理性が担保されている必要があります。
そういった意味で、「いま自分が取り組んでいるテーマを、最後まで責任を持って仕上げる」ということを、大切にして欲しいですね。そして、それができていれば、たとえ将来、研究分野が変わることがあったとしても、本質的にやるべきことは同じです。どう発想し、どう進め、どうまとめればよいのかが、自然と身についているはずです。
また、自分自身の研究テーマを考えることはもちろん、後輩のテーマを一緒に考えてあげて下さい。先ほども少しお話ししましたが、「テーマを発想する力」は、企業においても非常に大切です。
加えて、後輩を指導し、チームをマネジメントするような役割も、博士課程の方には求められることが多いですが、そういったことにも積極的に取り組んでもらえればと思います。
様々な経験を学生時代に積んでおくことは、決して無駄にはなりません。努力した分だけ、将来的に自分の強みとして必ず活きてくると思います。
鬼頭 ありがとうございます。最後のお話はまさに中間管理職の経験ということですね。人に教えることで自分も育つということもあるでしょうか。
永富 いいことをおっしゃってくださいました。本当にその通りで、後輩から何かを聞かれたときに知らないのは恥ずかしいので、必死に調べたことが多々ありました。教えることが学びになるということは、在学中にはなかなか気づきにくいことかもしれません。自分の研究が忙しいと、どうしても後輩のことまで気が回らなくなってしまいがちですが、やはり“教える側”に立つことで、自分の知識が強化されますね。
鬼頭 アドバイスの延長になりますが、よく博士学生の方とお話しすると、民間企業での研究活動のイメージができていない方も多くいらっしゃると感じます。アカデミアと民間企業での研究活動にはどのような違いがあるのでしょうか。
永富 サイエンスという視点での「チャンピオンデータ」では許されない、というのが民間企業における研究活動と言えるのかもしれません。
アカデミアの先生方からは怒られるかもしれませんが、アカデミアでは一番良いデータ、つまり「ここまでの結果が出せる」というデータも大変貴重です。再現性は当然必要ですが、それでも「サイエンスとしての可能性を示す」という意味で、チャンピオンデータは尊重すべきだと思っています。
一方で、民間企業の研究では、再現性が非常に重要視されます。つまり、「この範囲の値が、誰がやっても必ず出る」と保証できなければならず、アカデミアと民間企業とでは研究で力をかける部分が少し異なっています。
つまり、アカデミアでは「どこまで到達できるか」に向かってエネルギーを集中させますが、企業では「どこまで到達できるか」だけでなく、「下限はどこか」「その幅をどうコントロールするか」という点が同時に求められます。そのため、目指す方向性やマインドセットが、民間企業と大学ではやや異なると感じます。
また、研究テーマの立て方においても違いがあります。民間企業の研究でも、当然「サイエンスとしての面白さ」は重要ですが、「この研究成果を社会実装する」という視点が強く求められます。しかも、単なるスローガンや抽象的な話ではなく、具体的に「どう実装するのか」まで描く必要があり、ここはアカデミアと民間企業の研究で異なる部分だと思います。
鬼頭 それでは最後に、アサヒグループの研究職に興味を持った方に対してメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。
永富 「アサヒの研究職」というよりも、少し一般的なメッセージになりますが、進学か就職かを考えている修士課程の学生さんについては、もし純粋に研究や実験が好きだという気持ちがあるなら、博士課程に進むという選択肢は、一度真剣に検討してみて下さい。
「その先どうなるか」「将来どうなるか」といったことを、あまり考えすぎなくて良いと思います。10年後のことなんて誰にもわかりませんし、考えたとおりになるケースの方が少ないと思います。ですから、まずは今の気持ちと、博士課程に進学したあとの3〜4年後の自分に、どんな姿を期待するのか──そのくらいのスパンでイメージしてみると、より前向きに進んでいけると思います。10年後や20年後を考えすぎてしまうと、ついリスクばかりが気になって、チャレンジする気持ちが抑え込まれてしまうかもしれません。そうではなく、「3~4年後の自分はこんなふうに成長しているかもしれない」といった、未来の自分に対する期待を持ちながら進んでもらえたらと思います。民間企業の研究所としても、そうした前向きなマインドを持った方にぜひ来ていただきたいですね。
鬼頭 以上で、こちらからご用意したインタビューの質問はすべてです。本日は貴重なお話をありがとうございました。
アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社は、博士課程学生向けの長期インターンシッププログラム「ジョブ型研究インターンシップ」(※)の取り組みに参画しています。
直近の募集状況については専用システムにてご確認ください。
(※)プログラムの説明は、ジョブ型研究インターンシップ推進協議会HP、または各大学の担当部局にてご確認ください。
◆ インタビューのお相手:永富 康司 氏(アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社 代表取締役社長)
◆ 企業情報
社名:アサヒクオリティアンドイノベーションズ株式会社
代表者:代表取締役社長 永富 康司
本社所在地:〒302-0106 茨城県守谷市緑1-1-21
設立:2019年3月8日
こちらの記事は2025年6月9日に公開しており、記載されている情報が現在と異なる場合がございます。